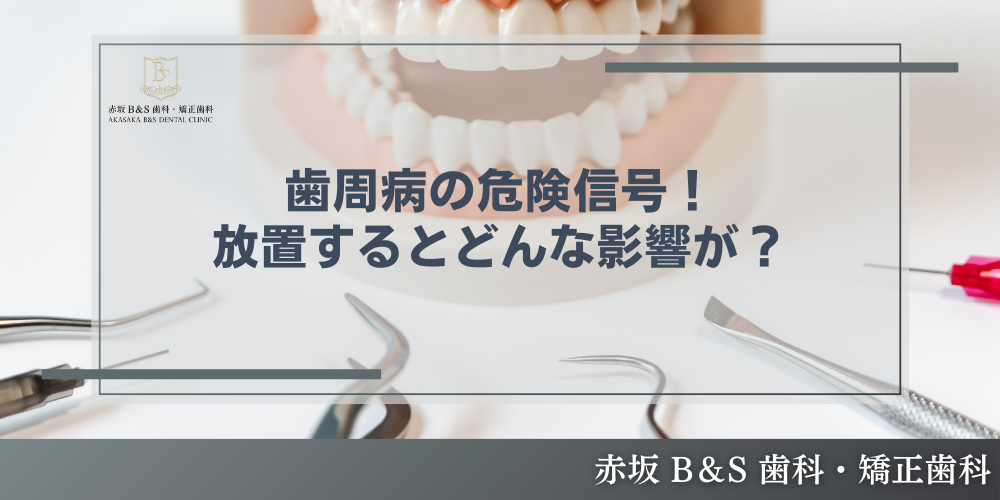 港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科「赤坂B&S歯科・矯正歯科」です。
港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科「赤坂B&S歯科・矯正歯科」です。
毎日の歯磨きで歯ぐきから血が出たり、ふとした時に口臭が気になったりすることはありませんか?「ちょっと疲れているだけかな」「一時的なものだろう」と軽く考えてしまうかもしれませんが、それは歯周病という病気のサインかもしれません。
歯周病は、放っておくと大切な歯を失うだけでなく、実は全身の健康にも深く関わる深刻な病気です。この病気は初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行していることがほとんどです。しかし、忙しい日々の中でも、ご自身の口の中の小さなサインに気づき、適切なケアを始めることで、手遅れになる前に進行を食い止めることができます。
この記事では、歯周病の初期症状から、放置することで起こり得る口の中や全身への影響、そして今日から始められる予防法までを分かりやすくご紹介します。大切な歯と健康な毎日を守るために、一緒に歯周病について理解を深め、早めの対策を始めていきましょう。
そもそも歯周病とは?静かに進行する口の中の病気
歯周病と聞くと、多くの人が歯の病だと考えがちですが、実は歯そのものではなく、歯を支える組織、つまり歯ぐきや顎の骨などが細菌によって破壊されていく感染症なのです。初期の段階では、痛みなどの目立った症状がほとんど現れないため、ご自身では気づかないうちに進行してしまうことが少なくありません。このため、歯周病は「サイレント・ディジーズ(静かなる病)」とも呼ばれ、気づかないうちに病状が悪化し、重症化してしまうケースも多く見られます。
歯周病が進行すると、歯ぐきの炎症だけでなく、最終的には歯を支える骨が溶けてしまい、歯がグラグラになって抜け落ちてしまうことさえあります。日々の忙しさの中で、ついつい口の中の小さな変化を見過ごしてしまいがちですが、この静かなる病について理解を深め、早期の段階で適切に対処することが、将来の健康な口元を守るために非常に重要です。
歯周病の原因は歯垢(プラーク)に潜む細菌
歯周病の最も大きな原因は、毎日のブラッシングで取り除ききれなかった「歯垢(プラーク)」に潜む細菌です。歯垢は単なる食べかすの残りではなく、実は数億もの細菌の塊で、ネバネバとした膜状になって歯の表面に付着しています。この歯垢に含まれる細菌が歯ぐきに感染すると、炎症が引き起こされ、歯ぐきが赤く腫れたり、出血しやすくなったりします。
もし歯垢が長時間放置されると、唾液中のミネラルと結合して「歯石」と呼ばれる硬い物質に変化します。歯石は歯ブラシでは取り除くことができず、表面がザラザラしているため、さらに歯垢がつきやすくなり、細菌の温床となって歯周病を悪化させる原因となります。つまり、歯垢の蓄積が歯周病の進行を招く悪循環の始まりなのです。
実は歯を失う最大の原因
多くの方が虫歯を歯を失う主な原因だと考えていますが、実は成人において歯を失う最大の原因は歯周病です。厚生労働省の調査によると、歯が抜ける原因の第1位は歯周病であり、虫歯を大きく上回っています。この事実は、歯周病が単なる口の中の不調ではなく、歯を失うという深刻な結果につながる病であることを明確に示しています。
歯周病は初期の段階では自覚症状が少ないため、気づいた時にはすでにかなり進行しているケースが少なくありません。そのため、「まだ大丈夫だろう」と軽く考えて放置してしまうと、取り返しのつかない事態になる可能性が高いのです。ご自身の歯を長く使い続けるためには、歯周病の早期発見と適切なケアが何よりも重要であることを認識していただく必要があります。
30代から要注意!年齢とともに高まる歯周病のリスク
歯周病は、特定の年齢層だけが気を付ければ良い病ではありませんが、特にリスクが高まる年代があります。一般的に、30代を迎える頃から歯周病にかかっている人の割合が増え始め、40歳以降になると急速に歯を失う主要な原因となります。実際、30代から60代にかけての歯周病の罹患率は、58%から78%へと顕著に増加するというデータも示されています。
これは、長年の食生活や口腔ケアの習慣、加齢による体の変化などが複合的に影響しているためと考えられます。忙しい日々の中で、つい自分の口の健康を後回しにしがちな方もいらっしゃるかもしれませんが、30代を過ぎたら、ぜひ一度ご自身の口腔内の状態に目を向け、歯周病のリスクが高まっている可能性を意識してみてください。早めに対策を始めることが、将来の健康な歯を守るカギとなります。
これって歯周病?見逃したくない危険信号セルフチェック
歯周病は初期段階では自覚症状が少ないため、ご自身の口の中の状態に意識を向けることがとても大切です。もしも、普段の生活の中で気になるサインに気づいたら、それは歯周病が静かに進行している警告かもしれません。これからご紹介する具体的な症状をセルフチェックし、ご自身の口の状態と照らし合わせてみてください。これらのサインを見逃さず、早期の対策につなげることが、ご自身の歯と全身の健康を守る第一歩となります。
歯ぐきからの出血や腫れ
歯周病の最も一般的なサインの一つに、歯磨きやフロスを使用している時に歯ぐきから血が出ることが挙げられます。健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっており、少々の刺激で出血することはありません。しかし、歯周病菌によって歯ぐきに炎症が起きると、赤く腫れ上がり、毛細血管がもろくなるため、少しのブラッシングや食事の摩擦でも簡単に出血するようになります。これは、歯ぐきが「SOS」を出している状態であり、「異常」のサインとして認識することが非常に重要です。出血は体の防御反応でもあるため、見過ごさずに注意深く観察してください。
口臭が気になるようになった
口臭は誰にでもあるものですが、歯周病による口臭は特徴的で、周囲の人にも不快感を与えることがあります。歯周病が進行すると、歯周ポケットと呼ばれる歯と歯ぐきの間の溝が深くなり、そこに歯周病菌が大量に増殖します。これらの細菌が、口の中に残ったタンパク質を分解する際に「メチルメルカプタン」などの揮発性硫黄化合物を生成します。これが、腐った卵のような、あるいは生ゴミのような特有の強い口臭の原因となります。一時的な食べ物による口臭とは異なり、持続的に不快な臭いがする場合は、歯周病が進行している可能性が高いと考えられます。
歯が長くなったように見える(歯ぐきの後退)
歯周病の進行によって、見た目にも変化が現れることがあります。鏡を見て「最近、歯が長くなったような気がする」と感じたら、それは歯ぐきの後退が原因かもしれません。歯周病が進行すると、歯を支えている顎の骨(歯槽骨)が細菌の出す毒素によって溶かされてしまいます。それに伴い、歯ぐきも下がってしまい、今まで歯ぐきに覆われていた歯の根元部分が露出して、歯全体が長く見えてしまうのです。歯ぐきの後退は見た目の問題だけでなく、露出した歯の根元は知覚過敏を引き起こしやすく、冷たいものがしみるようになることもあります。
歯がグラグラする、食べ物が挟まりやすい
歯がグラグラする、食べ物が頻繁に歯の間に挟まるようになった、といった症状は、歯周病がかなり進行しているサインです。歯周病によって歯を支える顎の骨が溶けてしまうと、歯がしっかりと固定されなくなり、不安定になって揺れ始めることがあります。また、歯ぐきが下がったり、歯の間の骨が溶けたりすることで、歯と歯の間に以前よりも大きな隙間ができ、食事の際に食べ物が詰まりやすくなります。これらの症状が見られる場合は、歯を失う危険性が高まっているため、一刻も早く歯科医院を受診し、適切な治療を受けることが重要です。
歯周病を放置すると起こる深刻な影響
歯周病は、歯ぐきの問題だけにとどまりません。放置してしまうと、単に歯を失うだけでなく、日々の生活の質(QOL)を大きく低下させ、さらには糖尿病や心臓病といった全身の様々な病のリスクを高めることが分かっています。ここでは、歯周病が口の中と全身にどのような深刻な影響を及ぼすのかを詳しく解説していきます。
口の中で起こる問題
歯周病が進行すると、まず口の中で様々な問題が引き起こされます。特に、歯を支える大切な骨が溶けてしまうこと、そして最終的に歯が抜け落ちてしまうという最も直接的な影響は避けたい事態です。これらの具体的な問題について、次の項目で詳しく見ていきましょう。
歯を支える骨(歯槽骨)が溶ける
歯周病が進行すると、歯をしっかりと支えている「歯槽骨(しそうこつ)」という顎の骨が、少しずつ溶けていってしまいます。これは、歯周病菌が出す毒素が歯ぐきに炎症を引き起こし、その炎症がさらに骨を破壊する細胞を活性化させてしまうために起こります。
この歯槽骨は、一度溶けてしまうと自然に元に戻ることはほとんどありません。骨が溶けてしまうと、歯を支える土台が弱くなり、歯がグラグラし始めます。そのため、早期に歯周病を発見し、治療を始めることが、歯槽骨の破壊を食い止める上で非常に重要になります。
最終的に歯が抜け落ちてしまう
歯周病による歯槽骨の破壊がさらに進むと、歯を支える土台が失われ、歯はますます不安定になります。最終的には、グラグラする歯が食事中や何気ない拍子に自然と抜け落ちてしまうことがあります。実際に、歯を失う原因の第1位は歯周病であり、特に40歳以降の成人の間でこの傾向は顕著です。
歯を失うことは、食べ物をしっかり噛めなくなるだけでなく、発音しにくくなったり、見た目が大きく変わったりと、日々の生活に非常に大きな影響を与えます。美味しく食事を楽しんだり、自信を持って会話したりするためにも、歯を失う前に適切な治療とケアを行うことが大切です。
全身の健康に及ぼす影響
歯周病は口の中だけの問題だと考えられがちですが、実は全身の健康にも深く関わっています。歯周病菌や、歯ぐきの炎症によって作られる物質が血流に乗って全身を巡り、様々な病を引き起こしたり、既存の病を悪化させたりするリスクがあることが分かってきています。ここでは、歯周病が全身に及ぼす影響について見ていきましょう。
糖尿病との深い関係性
歯周病と糖尿病は、お互いに影響を及ぼし合う「双方向の関係」にあることが知られています。歯周病による歯ぐきの炎症は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの働きを阻害し、血糖コントロールを悪化させてしまうことがあります。これにより、糖尿病の症状が進行しやすくなるのです。
一方で、糖尿病で高血糖の状態が続くと、体の免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。これにより、歯周病菌が増殖しやすくなり、歯周病の進行を加速させてしまうこともあります。糖尿病をお持ちの方は、歯周病の治療と管理を徹底することが、全身の健康管理においても非常に重要だと言えるでしょう。
心臓病や脳卒中のリスク上昇
歯周病が、心臓病や脳卒中といった命に関わる病のリスクを高める可能性も指摘されています。歯周病の原因菌が歯ぐきの血管から体内に入り込み、血液に乗って全身を巡ることがあります。
これらの細菌や炎症物質が血管の壁に悪影響を与え、動脈硬化(血管が硬くなり、狭くなる状態)を促進する「プラーク(アテローム)」の形成に関与すると考えられています。動脈硬化が進むと、血管が詰まりやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞といった重大な病を引き起こすリスクが高まるのです。口腔内の健康は、全身の血管の健康にもつながっていると言えるでしょう。
肺炎、早産など他の疾患との関連
歯周病は、糖尿病や心臓病以外にも、様々な全身疾患との関連が研究されています。特に高齢者の方の場合、歯周病菌が唾液と一緒に誤って気管に入ってしまうことで「誤嚥性肺炎」を引き起こすリスクが高まります。口腔内を清潔に保つことは、肺炎予防にもつながるのです。
また、妊娠中の女性にとっては、歯周病が早産や低体重児出産のリスクを高める可能性が報告されています。歯周病による炎症性物質が、子宮の収縮を促す作用を持つためと考えられています。このように、歯周病は年齢や性別を問わず、幅広い層の健康に影響を及ぼす可能性があるため、日頃からのケアが大切です。
歯周病は予防できる!今日から始めるセルフケア
これまで歯周病がもたらす危険性について解説してきましたが、恐れることはありません。歯周病は日々の適切なケアと生活習慣の見直しによって、十分に予防できる病です。今日からでも始められる具体的な対策を実践することで、健康な歯と体を長く維持することができます。
このセクションでは、ご自宅で実践できる効果的なセルフケアの方法と、歯周病のリスクを高める生活習慣を見直すヒントをご紹介します。一つ一つの取り組みは小さなことかもしれませんが、継続することで大きな予防効果につながります。
毎日の正しい歯磨きが基本
歯周病予防の最も基本的な対策は、毎日の丁寧な歯磨きです。単に歯ブラシを口に入れるだけではなく、「正しく」磨くことが非常に重要になります。ここでは、歯周病の原因となる歯垢(プラーク)を効率的に除去するための、正しい歯磨きのポイントについて詳しく見ていきましょう。
歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨く
歯周病菌は、歯と歯ぐきの間の溝である「歯周ポケット」に潜んで繁殖します。そのため、歯周病予防において最も重要なのは、この歯と歯ぐきの境目をしっかりと磨き、歯垢を除去することです。
効果的な磨き方としては、「バス法」が推奨されます。これは、歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの境目に約45度の角度で当て、軽い力で小刻みに振動させるように動かす方法です。歯ブラシの毛先が歯周ポケットの奥に入り込むように意識し、一本一本丁寧に磨くように心がけてください。力を入れすぎると歯ぐきを傷つけてしまうため、優しく、しかし確実に歯垢をかき出すイメージで磨くことが大切です。
歯間ブラシやデンタルフロスの活用
歯ブラシだけでは、歯の表面の約6割の歯垢しか除去できないと言われています。特に、歯と歯の間は歯ブラシの毛先が届きにくく、歯垢が残りやすい場所です。ここに残った歯垢が歯周病を進行させる大きな原因となります。
そこで重要になるのが、歯間ブラシやデンタルフロスといった補助的な清掃用具の活用です。歯間ブラシは、歯と歯の間の隙間の大きさに合わせて様々なサイズがありますので、ご自身の歯に合ったものを選びましょう。フロスは、歯と歯の接触面や、歯ぐきの下のわずかな隙間に溜まった歯垢を効果的に除去できます。
これらの清掃用具を毎日の歯磨きに加えることで、歯垢除去率を格段に向上させ、歯周病予防に大きく貢献することができます。使用方法が分からない場合は、歯科医院で指導を受けることをおすすめします。
生活習慣の見直しも大切
歯周病は、口の中だけの問題ではなく、全身の健康状態や日々の生活習慣が大きく影響します。喫煙やストレス、食生活の乱れといった生活習慣は、歯周病のリスクを高め、進行を早める要因となります。口腔ケアと合わせて、これらの生活習慣を見直すことが、歯周病予防には不可欠です。
禁煙やストレス管理
喫煙は、歯周病の最大のリスク因子の一つとして知られています。タバコに含まれる有害物質は、歯ぐきの血流を悪化させ、免疫細胞の働きを低下させるため、歯周病菌に対する抵抗力を弱めてしまいます。また、治療の効果も出にくくなる傾向があります。禁煙することは、歯周病だけでなく全身の健康にとっても非常に有効な予防策です。
さらに、過度なストレスも歯周病を悪化させる要因となります。ストレスは体の免疫機能に影響を与え、歯周病菌の活動を活発にさせることがあります。日々の生活の中で、リラックスできる時間を持つことや、適度な運動を取り入れるなど、ストレスを上手に管理することも、歯周病予防につながります。
バランスの取れた食事
歯や歯ぐきの健康を保つためには、栄養バランスの取れた食事が重要です。特に、歯ぐきの健康維持に必要なビタミンCや、骨を強くするカルシウムなどを意識的に摂取しましょう。また、よく噛んで食べることは、唾液の分泌を促し、口の中の自浄作用を高める効果があります。唾液には、食べかすを洗い流したり、細菌の増殖を抑えたりする働きがあるため、よく噛む習慣は歯周病予防にとても有効です。
間食を摂る際は、だらだらと食べ続けず、時間を決めて摂るように心がけましょう。糖分の多い飲食物を頻繁に摂取すると、口の中が酸性に傾きやすくなり、虫歯だけでなく歯周病のリスクも高まります。
「もしかして歯周病かも?」と思ったらすぐに歯科医院へ
日々のセルフケアは歯周病予防の基本ですが、もし歯ぐきの出血や腫れ、口臭など、これまでご紹介したような気になる症状が見られる場合は、自己判断せずにすぐに歯科医院を受診することが大切です。
歯周病は初期段階では自覚症状がほとんどなく、知らないうちに進行していることも少なくありません。忙しい日々の中で歯科医院に行く時間がないと感じるかもしれませんが、早期に専門家の診断を受けることで、症状が軽いうちに適切な治療を始められ、将来的に歯を失うリスクを大きく減らすことができます。
歯周病の進行段階と治療法
歯科医院では、歯周病の進行度合いに応じて様々な治療が行われます。歯周病は一度進行してしまうと自然に治ることはなく、放置すると徐々に悪化していく病です。そのため、ご自身の歯周病がどの段階にあるのかを正確に把握し、その段階に合わせた治療を受けることが非常に重要になります。
軽度(歯肉炎)から重度(歯周炎)までの流れ
歯周病は、大きく分けて骨の破壊が始まっていない「歯肉炎」と、骨の破壊が進行している「歯周炎」の2つの段階に分けられます。
まず「歯肉炎」は、歯垢が原因で歯ぐきが炎症を起こしている状態です。歯ぐきが赤く腫れたり、歯磨き時に出血したりしますが、この段階ではまだ歯を支える骨(歯槽骨)への影響はありません。歯肉炎の段階であれば、歯科医院での専門的なクリーニングと、ご自身による正しい歯磨きなどのセルフケアを徹底することで、健康な歯ぐきの状態に戻すことが十分に可能です。この時期に治療を開始できると、治療にかかる時間や費用も抑えられます。
しかし、歯肉炎を放置すると「歯周炎」へと進行してしまいます。歯周炎では、歯ぐきの炎症がさらに広がり、歯周ポケットが深くなります。この深い歯周ポケットの内部で細菌が繁殖し、歯を支える歯槽骨が溶け始めるのです。軽度の歯周炎から中度、そして重度へと進行するにつれて、歯槽骨の破壊は加速し、最終的には歯がグラグラになり、抜け落ちてしまうこともあります。歯周炎の治療には、歯周ポケット内の歯垢や歯石を除去する「歯周基本治療」や、場合によっては外科的な処置が必要になることもあります。
手遅れになる前に相談を
「自分の歯周病はもう手遅れかもしれない」と不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、歯周病治療における「手遅れ」の判断は非常に難しく、一概には言えません。たとえ重度の歯周病と診断されても、現代の歯科医療では様々な治療法があり、高度な技術を持つ歯科医師であれば、抜歯をせずに歯を残せる可能性も十分にあります。
大切なのは、ご自身の判断で諦めてしまわないことです。まずは歯科医院を受診し、現在の口の中の状態を正確に把握してもらうことが第一歩です。歯科医師は、歯周病の進行度合いや口全体の状況を詳しく診査し、その方に合った最適な治療計画を提案してくれます。勇気を出して一歩踏み出し、専門家に相談することで、歯を失うという最悪の事態を避けることができるかもしれません。
定期的な歯科検診の重要性
歯周病の治療が終わったからといって、それで全てが終わりではありません。歯周病は再発しやすい病のため、治療後のメンテナンスと予防が非常に重要になります。そのために欠かせないのが、定期的な歯科検診です。
定期検診では、ご自宅での歯磨きでは落としきれない歯垢や歯石を専門的な器具で除去する「プロフェッショナルクリーニング(PMTC)」を受けられます。また、歯科医師や歯科衛生士が、歯周病の再発の兆候がないか、歯ぐきの状態や噛み合わせなどを細かくチェックしてくれます。自覚症状がなくても歯周病が進行しているケースは少なくありませんので、問題が大きくなる前に早期発見・早期治療を行うことが、ご自身の歯を長く健康に保つ上で最も効果的かつ経済的な方法と言えます。
忙しい毎日を送る中で、定期的に歯科医院に通うのは大変だと感じるかもしれません。しかし、将来的に多くの時間と費用、そして痛みや苦痛を伴う治療を受けることを考えれば、数ヶ月に一度の定期検診は、ご自身の健康な生活への大切な投資となります。ぜひ、今日から定期検診を習慣にし、健康な口内環境を維持していきましょう。
まとめ:健康な歯と体のため、歯周病のサインを見逃さないで
これまでお伝えした通り、歯周病は、歯ぐきや歯を支える骨が細菌によって破壊されていく感染症です。初期段階では自覚症状がほとんどなく、「サイレント・ディジーズ(静かなる病)」とも呼ばれるほど静かに進行します。しかし、歯を失う最大の原因であるだけでなく、糖尿病、心臓病、脳卒中、肺炎、早産といった全身のさまざまな病のリスクを高める深刻な問題です。
しかし、歯周病は決して防げない病ではありません。毎日の正しい歯磨きはもちろんのこと、歯間ブラシやデンタルフロスの活用、禁煙やストレス管理、バランスの取れた食事といった生活習慣の見直しが予防に繋がります。
もし歯ぐきからの出血、口臭、歯ぐきの後退、歯のグラつきなど、少しでも気になるサインがあれば、それは歯周病の危険信号かもしれません。ご自身で「手遅れかもしれない」と判断せず、できるだけ早く歯科医院を受診し、専門家にご相談ください。
歯科医院では、歯周病の進行度合いに応じた適切な治療が受けられるだけでなく、定期的な検診とプロフェッショナルクリーニングによって、病の早期発見と予防、そして再発防止に繋がります。健康な歯と体を維持するために、歯周病のサインを見逃さず、積極的なセルフケアと定期的な歯科検診を習慣にしましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
近藤 光 | Kondo Hikaru東京歯科大学卒業後、医療法人社団歯友会赤羽歯科に勤務し、その後、池袋診療所をはじめとする複数の歯科医院で経験を積み、フリーランス矯正歯科医として活動を開始。
その後、カメアリデンタル、デンタルクリニックピュア恵比寿、茅ヶ崎アルカディア歯科・矯正歯科、フォルテはにゅうモール歯科、舞浜マーメイド歯科など、多くの歯科医院で勤務を重ね、2023年12月赤坂B&S歯科・矯正歯科 開院。
【所属】
- 日本顎咬合学会
- 日本審美歯科学会
- 日本成人矯正歯科学会
- 日本舌側矯正歯科学会
- 日本メタルフリー学会
- 日本接着歯科学会
- 日本アライナー矯正研究会
- 日本顎顔面美容医療協会 認定医
- ICOI(国際口腔インプラント学会)
- 日本一般臨床矯正研究会
- OTEXE
- インディアナ大学歯学部矯正科認定医
【略歴】
- 東京歯科大学 卒業
- 医療法人社団歯友会赤羽歯科
- 同法人池袋診療所 入局
- 医療法人スマイルコンセプト
- 高田歯科インプラントセンター
- しんみ歯科
- 医療法人社団優綾会カメアリデンタル 矯正歯科担当医
- デンタルクリニックピュア恵比寿 矯正歯科担当医
- 医療法人社団角理会 茅ヶ崎アルカディア歯科・矯正歯科 矯正歯科担当医
- 医療法人恵優会フォルテはにゅうモール歯科 矯正歯科担当医
- 舞浜マーメイド歯科 矯正歯科担当医
- 医療法人恵優会かすかべモール歯科 矯正歯科担当医
- レフィーノデンタルクリニック 矯正歯科担当医
- 医療法人社団カムイ会柏なかよし矯正歯科・小児歯科 矯正歯科担当医
港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科
『赤坂B&S歯科・矯正歯科』
住所:東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル1・2F
TEL:03-5544-9426

