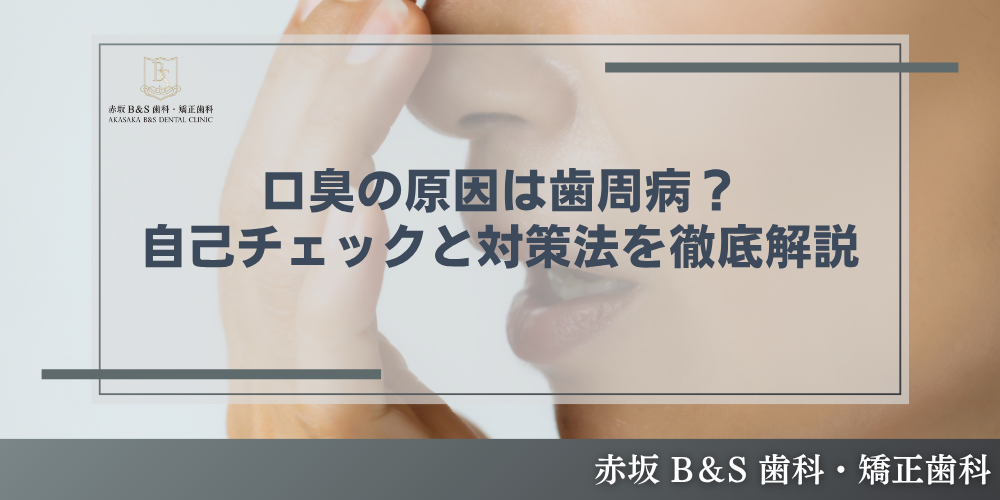 港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科「赤坂B&S歯科・矯正歯科」です。
港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科「赤坂B&S歯科・矯正歯科」です。
毎日しっかり歯磨きをしているのに、なぜか口臭が気になる、または家族から口臭を指摘された経験はありませんか。もしかするとその口臭、歯周病が原因かもしれません。このコラムでは、口臭と歯周病の意外な関係性から、歯周病がどのような病気なのか、そしてなぜ口臭を引き起こすのかを詳しく解説いたします。さらに、ご自宅で簡単にできる歯周病のセルフチェック方法や、今日から実践できる具体的な予防・対策法までご紹介します。この記事を読み進めることで、歯周病に関する正しい知識を身につけ、自信を持って口元を見せられるように、健康な口腔環境を維持するためのヒントが得られるでしょう。
その口臭、歯周病が原因かも?気になる関係性とは
口臭は誰もが一度は経験する悩みですが、飲食による一時的なものや起床時の生理的なものとは異なり、歯磨きをしてもなかなか消えないしつこい口臭に悩まされている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は、そうした頑固な口臭の原因は、歯周病という病気が潜んでいる可能性も考えられます。
このセクションでは、なぜ歯周病が口臭の主な原因の一つとなるのか、その気になる関係性について詳しく解説します。歯周病によって発生する特有の口臭のメカニズムを理解することで、ご自身の口腔内の状態に目を向けるきっかけとしていただければ幸いです。
歯周病とは?歯を支える組織が壊れていく病気
歯周病とは、歯そのものではなく、歯ぐきや歯を支える骨などの周囲の組織(歯周組織)が炎症を起こす病気です。初期の歯周病では、歯ぐきの赤み、腫れ、出血といった症状が見られますが、多くの場合、痛みなどの自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行してしまうことがあります。
歯周病の主な原因は、歯の表面や歯周ポケット(歯と歯ぐきの境目の溝)に付着するプラーク、すなわち細菌の塊です。このプラーク中の細菌が毒素を出すことで歯周組織に炎症を引き起こし、やがて歯を支える大切な骨である歯槽骨(しそうこつ)が溶かされてしまいます。歯槽骨が溶けてしまうと、歯はグラグラと不安定になり、最終的には歯を失う原因となってしまうのです。
日本人の成人の約8割が歯周病に罹患していると言われるほど身近な病気であり、年齢が上がるにつれてその割合は高くなる傾向にあります。進行すると歯の喪失だけでなく、全身の健康にも様々な悪影響を及ぼす可能性があるため、早期の発見と適切なケアが非常に重要です。
なぜ歯周病で口臭が発生するのか
歯周病が進行すると口臭が強くなる原因は、主に歯周ポケットの奥深くに潜む歯周病菌にあります。これらの歯周病菌の多くは、酸素を嫌う嫌気性菌(酸素が少ない場所を好む細菌)であり、歯周ポケットのような酸素の少ない環境で活発に活動します。
歯周病菌は、歯周ポケット内の剥がれ落ちた細胞や血液、食べカスなどに含まれるタンパク質を分解する際に、「揮発性硫黄化合物(VSC)」というガスを発生させます。この揮発性硫黄化合物こそが、卵が腐ったような、あるいは玉ねぎが腐ったような独特で不快な口臭の主な原因物質なのです。特に「メチルメルカプタン」と呼ばれる成分は、口臭の中でも特に強い臭気を放つことで知られています。
歯周病が進行して歯周ポケットが深くなると、嫌気性菌にとってさらに住みやすい環境となり、より多くの菌が増殖します。その結果、揮発性硫黄化合物の産生量も増え、口臭も一層強くなってしまうという悪循環に陥ります。そのため、歯周病の治療は、口臭改善にも直結する重要なステップとなります。
自宅でできる歯周病セルフチェックリスト
歯周病は、初期段階ではほとんど自覚症状がないため、ご自身で気づくのが難しい病気として知られています。そのため、「もしかしたら自分も?」と感じていても、なかなか歯科医院に行くきっかけがない方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、日頃からご自身の口の中の状態に意識を向け、わずかな変化のサインに気づくことが、歯周病の早期発見と早期対策につながる大切なポイントです。
このセクションでは、ご自宅で簡単にできる歯周病のセルフチェックリストをご紹介します。「歯ぐき」「歯」「口の中の感覚」という3つの観点から、ご自身の口腔状態を客観的に見つめ直すための項目をまとめました。ぜひ、このチェックリストを活用して、ご自身の口の中の健康状態を確認してみてください。
歯ぐきの状態をチェック
歯周病の初期症状は、歯ぐきに現れることが最も多いです。ご自身の歯ぐきの色や形、触れたときの感覚などを注意深く観察してみましょう。健康な歯ぐきは薄いピンク色で引き締まっており、弾力があります。
歯ぐきが赤く腫れている、または紫色っぽくなっている
歯磨き中や硬いものを食べた時に歯ぐきから出血がある
歯ぐきがむずがゆい、または違和感がある
歯ぐきから膿(うみ)が出ることがある
歯ぐきが下がって、歯が長くなったように見える
これらの項目に当てはまる場合、歯周病が進行している可能性があります。特に、歯ぐきの赤みや腫れ、出血は歯周病の典型的なサインです。また、歯ぐきが下がって歯の根元が見えるようになるのは、歯を支えている骨(歯槽骨)が溶け始めている兆候かもしれません。
歯の状態をチェック
歯ぐきの状態だけでなく、歯そのものや、歯と歯ぐきの間の変化も歯周病の進行を示す重要なサインとなります。以下のような項目がないか確認してみましょう。
歯がグラグラと動く、または以前よりも揺れが大きくなった
歯と歯の間に隙間ができてきた、または食べ物が挟まりやすくなった
特定の歯で噛むと痛みがある、または以前と違う違和感がある
歯がグラグラするのは、歯を支える土台である歯槽骨が溶けて、歯が安定性を失っている状態です。また、歯と歯の間に隙間ができるのも、歯周組織の破壊によって歯の位置がずれたり、歯ぐきが下がったりしている可能性が考えられます。噛んだ時の痛みや違和感は、歯周組織の炎症が歯の根元にまで及んでいるサインかもしれません。
口の中の感覚や臭いをチェック
口臭や口の中の不快感も、歯周病の重要な手がかりとなります。これらの症状は、歯周病菌の活動が活発になっているサインである可能性があります。
朝起きた時、口の中がネバネバする
口の中が乾きやすいと感じる
口臭がする、または家族や親しい人から口臭を指摘されたことがある
朝起きた時の口のネバつきは、睡眠中に唾液の分泌量が減り、歯周病菌が増殖した結果として生じやすい症状です。口の中の乾燥も唾液による自浄作用が低下し、細菌が繁殖しやすい環境となるため、歯周病のリスクを高めます。そして、口臭は歯周病菌が作り出す「揮発性硫黄化合物」という物質が原因で発生します。特に、歯磨きをしてもなかなか消えないしつこい口臭がある場合は、歯周病が原因である可能性が高いと言えるでしょう。
なぜ歯周病になるの?主な原因を解説
歯周病は、お口の中の細菌が原因で引き起こされる病気ですが、それ以外にも病気の進行を早めたり、発症しやすくなったりするさまざまな要因があります。ここでは、歯周病の主な原因である細菌の塊「プラーク」について詳しく見ていきましょう。さらに、私たちの日常生活や全身の状態がどのように歯周病に影響を与えるのか、詳しく掘り下げていきます。
歯周病は一度かかってしまうと自然に治ることはありません。そのため、これらの原因を知り、適切に対処することで、歯周病を予防し、進行を食い止めることがとても大切になります。
最大の原因は歯垢(プラーク)と歯石
歯周病の最も直接的で大きな原因となるのが、歯の表面や歯周ポケットに付着する「歯垢(プラーク)」と、それが硬化した「歯石」です。歯垢は単なる食べかすではなく、細菌と、細菌が作り出すネバネバした物質の塊であり、その中には歯周病の原因となる細菌が数多く潜んでいます。
歯磨きが不十分だと、この歯垢が歯と歯ぐきの境目や歯周ポケットの中に溜まり、歯周病菌が繁殖しやすい環境を作り出します。そして、歯垢が除去されずに時間が経つと、唾液中のミネラルと結合して硬くなり「歯石」へと変化します。歯石の表面は非常にザラザラしているため、さらに歯垢が付着しやすくなり、歯周病の進行を加速させる悪循環を生み出してしまうのです。
この歯石は、一度形成されてしまうとご自身での歯磨きでは除去することができません。歯科医院で専用の器具を使った専門的なクリーニングが必要となります。歯垢や歯石を放置することは、歯周病が進行する最大の要因となりますので、日々の丁寧な歯磨きと、定期的な歯科検診が非常に重要になります。
歯周病を悪化させる様々なリスク要因
歯周病の直接的な原因は歯垢(プラーク)と歯石ですが、これらが付着しやすい環境を作ったり、歯周病の進行を助けたりするさまざまな「リスク要因」が存在します。プラークコントロールが歯周病治療の基本であることに変わりはありませんが、これらのリスク要因が重なることで、歯周病はさらに悪化しやすくなります。ここでは、具体的なリスク要因を「生活習慣」「全身の病気」「口内環境」「その他の要因」に分けて詳しく解説していきます。
生活習慣(喫煙、ストレス、食生活)
私たちの日常の生活習慣は、歯周病の発症や進行に大きく関わっています。特に「喫煙」「ストレス」「食生活」の3つは、歯周病のリスクを高める主要な要因として知られています。
まず「喫煙」は、歯周病にとって非常に危険なリスク要因です。タバコに含まれるニコチンなどの有害物質は、歯肉の血管を収縮させて血流を悪くし、歯周組織への酸素や栄養の供給を妨げます。これにより、歯肉の免疫力が低下し、歯周病菌に対する抵抗力が弱まります。また、喫煙は傷の治りを悪くするため、歯周病治療後の回復も遅らせてしまうことが知られています。喫煙者は非喫煙者に比べて歯周病の進行が早く、重症化しやすい傾向にあります。
次に「ストレス」も歯周病に悪影響を及ぼします。強いストレスは体の免疫機能を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱める要因となります。ストレスを感じると、無意識のうちに歯を食いしばったり、歯ぎしりをしたりすることもあり、これらが歯周組織に過剰な負担をかけ、歯周病を悪化させる可能性もあります。
「食生活」においては、栄養バランスの偏りが歯肉の健康に影響を与えることがあります。特にビタミンやミネラルが不足すると、歯肉の抵抗力が低下し、炎症が起きやすくなります。また、糖質の多い食事は虫歯だけでなく、歯周病菌の栄養源にもなるため注意が必要です。
全身の病気(糖尿病など)との関連
歯周病は口の中だけの問題ではなく、実は全身の健康と深く関わっていることが分かっています。中でも「糖尿病」との関連性は特に注目されており、歯周病と糖尿病は互いに悪影響を及ぼし合う「双方向の関係」にあると言われています。
糖尿病患者さんは、高血糖状態が続くことで免疫機能が低下し、感染症にかかりやすくなります。このため、歯周病菌に対しても抵抗力が弱まり、歯周病が発症・進行しやすくなる傾向にあります。実際に、糖尿病患者さんの歯周病の罹患率は健常者に比べて高く、重症化しやすいことが示されています。
さらに、歯周病の炎症が糖尿病を悪化させることも知られています。歯周病菌が出す毒素や、歯肉の炎症によって生じるサイトカインという物質が血流に乗って全身に広がることで、インスリンの働きを阻害し、血糖コントロールを困難にさせてしまうのです。そのため、歯周病を治療することは、糖尿病の改善にも繋がる可能性があるとされています。全身の健康を維持するためにも、口腔ケアは非常に重要な役割を担っています。
口内環境(歯並び、口呼吸、不適合な被せ物)
歯周病は、お口の中の環境によってもリスクが高まります。特に、プラークが溜まりやすい特定の口内環境は、歯周病の進行を助長することがあります。
まず「歯並びの悪さ」は、歯周病のリスクを高める大きな要因です。歯並びがデコボコしていると、歯ブラシの毛先が届きにくい場所ができ、どうしても磨き残しが多くなってしまいます。これによりプラークが蓄積しやすくなり、歯周病菌が繁殖する絶好の環境を提供してしまうのです。また、歯並びが悪いと食べ物が挟まりやすくなることも、歯周病のリスクを高めます。
次に「口呼吸」も、お口の健康に悪影響を及ぼします。口呼吸が習慣になっていると、お口の中が乾燥しやすくなります。唾液には、お口の中を洗い流す「自浄作用」や、細菌の増殖を抑える「抗菌作用」がありますが、口が乾燥することでこれらの働きが低下し、歯周病菌が繁殖しやすい環境が作られてしまいます。
また「不適合な被せ物や詰め物」も、プラークの温床となることがあります。歯と被せ物・詰め物の間に段差や隙間があると、そこにプラークが引っかかりやすくなり、歯磨きでは除去しにくくなります。これにより、歯周病だけでなく二次的な虫歯のリスクも高めてしまいます。
さらに「歯ぎしり」や「食いしばり」も、歯周組織に過度な負担をかけることで、歯周病を悪化させる一因となることがあります。これらの習慣は、歯を支える骨にダメージを与え、歯周病の進行を早める可能性があります。
その他(遺伝、加齢、ホルモンバランス)
歯周病には、私たちの努力では変えられない、しかし知っておくべきリスク要因も存在します。それは「遺伝的要因」「加齢」、そして「ホルモンバランスの変化」です。
「遺伝的要因」は、歯周病の発症や進行に影響を与える可能性があります。ご家族に歯周病の人が多い場合、体質的に歯周病になりやすい傾向があるかもしれません。特定の遺伝子が歯周病への感受性を高めることが研究で示されており、家族歴がある方はより一層の注意と早期からの予防的ケアが推奨されます。
「加齢」も歯周病の重要なリスク要因の一つです。年齢を重ねるにつれて歯肉は徐々に下がりやすくなり、唾液の分泌量も減少することがあります。また、長年の生活習慣の積み重ねや、歯周病菌にさらされる期間が長くなることで、歯周病の罹患率は年齢とともに高まる傾向にあります。55歳以上の方では、半数以上が歯周病に罹患しているというデータもあります。
さらに「ホルモンバランスの変化」も歯周病に影響を与えます。特に女性の場合、妊娠中や更年期にはホルモンバランスが大きく変動します。妊娠中はプロゲステロンというホルモンの分泌が増加し、特定の歯周病菌が増殖しやすくなるため、歯肉が炎症を起こしやすくなります(妊娠性歯肉炎)。また、更年期にはエストロゲンの減少により骨密度が低下しやすくなり、歯を支える骨にも影響を及ぼす可能性があります。
放置は危険!歯周病が引き起こす口臭以外のリスク
歯周病は、多くの方が悩む口臭の原因となるだけでなく、放置すると口の中だけでなく、全身の健康にまで深刻な影響を及ぼす可能性があります。歯周病は初期段階では自覚症状が少ないため、気づかないうちに進行し、取り返しのつかない事態に発展することも少なくありません。
このセクションでは、歯周病を放置した場合に起こりうる「歯の喪失」という直接的なリスクと、全身のさまざまな病気との関連性について詳しく解説していきます。歯周病が単なるお口の問題ではないという認識を深め、その本当の怖さを理解していただくことで、早期の対策と継続的なケアの重要性を改めて感じていただけるかと思います。
歯が抜ける可能性
歯周病が進行すると、最終的に歯を失ってしまう可能性があります。実際、歯周病は成人が歯を失う最大の原因の一つと言われています。歯周病菌が出す毒素によって、歯を支えている歯ぐき(歯肉)だけでなく、さらに奥にある骨(歯槽骨)が徐々に溶かされていくのが、この病気のメカニズムです。
歯槽骨は、歯がしっかりと根を張るための土台です。この土台が溶けて失われると、歯は安定性を保てなくなり、次第にグラグラと動揺し始めます。最初は少しのぐらつきでも、病気が進行するにつれてその動きは大きくなり、最終的には自然に抜け落ちてしまったり、食事の際に痛みが生じて抜歯せざるを得なくなったりします。
歯周病は自覚症状が乏しく、痛みなどの症状が現れる頃には、すでに歯槽骨がかなり溶けてしまっているケースが少なくありません。そのため、「気づいた時には手遅れ」という状況にならないよう、日頃からの注意と早期発見・早期治療が非常に重要となります。
全身の健康への影響(心血管疾患・糖尿病の悪化など)
歯周病は、お口の中だけの問題に留まらず、全身の健康にまで悪影響を及ぼすことが近年の研究で明らかになってきています。歯周病菌や、それによって引き起こされる炎症物質が、歯肉の毛細血管から血流に乗って全身を巡ることで、さまざまな病気のリスクを高めることが分かっています。
特に注目されているのが、心血管疾患との関連です。歯周病菌や炎症物質が血管に入り込むことで、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や脳梗塞といった重篤な病気を引き起こすリスクを高めることが報告されています。また、歯周病と糖尿病は「双方向性」の関係にあることが知られています。糖尿病患者さんは感染症への抵抗力が低下しているため歯周病になりやすく、歯周病が悪化すると、炎症によってインスリンの働きが阻害され、血糖コントロールがさらに難しくなるという悪循環に陥る可能性があります。
その他にも、歯周病菌が気管から肺に侵入することで起こる誤嚥性肺炎のリスクや、妊娠中の女性においては早産や低体重児出産のリスクを高める可能性も指摘されています。これらのことから、歯周病のケアは、美しい口元や口臭の改善だけでなく、全身の健康を守る上で非常に重要な役割を担っていると言えるでしょう。
今日から始める!歯周病の予防と対策法
歯周病は、適切な対策を講じることで予防ができ、進行を食い止めることも可能な病気です。口臭や歯ぐきの異常を感じ始めた方も、これから紹介する予防法と対策法を実践することで、健康な口内環境を取り戻すことができます。歯周病ケアでは、ご自身で行う日々の「セルフケア」と、歯科医院で専門家が行う「プロフェッショナルケア」の両方が非常に重要になります。
このセクションでは、具体的なセルフケアとして正しい歯磨きの方法や歯間清掃の重要性、そしてプロフェッショナルケアとしての定期的な歯科検診の内容、さらに歯周病のリスクを減らすための生活習慣の改善について詳しく解説していきます。
基本のセルフケア:毎日の歯磨きを見直す
歯周病予防の基本中の基本は、毎日の歯磨きです。しかし、多くの方が自己流の歯磨きで、歯垢(プラーク)を十分に除去できていないことがあります。「磨いている」つもりでも「磨けていない」という状況は、歯周病を進行させる大きな原因となります。この機会に、ご自身の歯磨き方法が本当に効果的であるかを見直し、これから紹介する正しい歯ブラシの当て方や歯間清掃の重要性を理解して、日々のケアを向上させましょう。
正しい歯ブラシの当て方と動かし方
歯周病予防において最も重要なのは、歯と歯ぐきの境目に付着した歯垢を効率的に除去することです。まず、歯ブラシの毛先を歯と歯ぐきの間に45度の角度で当ててください。この角度で歯ブラシを軽く押し当てると、毛先が歯周ポケットにわずかに入り込み、そこに潜む歯垢をかき出すことができます。
次に、軽い力で小刻みに歯ブラシを動かす「バス法」を実践しましょう。歯ブラシを大きく動かすのではなく、1~2本の歯に対して毛先が振動するようなイメージで、細かく動かすことがポイントです。ゴシゴシと強い力で磨くと、歯ぐきを傷つけたり、歯の表面が削れたりする原因になりますので、優しく丁寧に磨くことを心がけてください。
歯間ブラシ・デンタルフロスの活用
歯ブラシだけでは、歯と歯の間の歯垢を完全に除去することはできません。歯間部はプラークが最も残りやすく、歯周病が進行しやすい場所の一つです。そのため、歯ブラシと合わせて「歯間ブラシ」や「デンタルフロス」といった補助清掃用具を毎日使用することが非常に重要になります。
歯間ブラシは、歯と歯の隙間に挿入して歯垢をかき出すもので、隙間の広さに合わせてサイズを選ぶことが大切です。無理なく通せるサイズのものを使いましょう。デンタルフロスは、細い繊維を歯間に通し、歯の側面や歯ぐきの境目の歯垢を絡め取ります。特に、歯間ブラシが入らないような狭い隙間や、歯と歯ぐきの境目にも効果的です。これらの清掃用具を毎日の歯磨きにプラスすることで、歯周病予防効果を格段に高めることができます。
プロフェッショナルケア:定期的な歯科検診
ご自宅でのセルフケアだけでは、歯周病を完全にコントロールすることは困難です。なぜなら、歯ブラシでは除去できない「歯石」の存在や、どうしても磨き残しが生じてしまう部分があるからです。そこで不可欠となるのが、歯科医院で専門家による「プロフェッショナルケア」を定期的に受けることです。
定期的な歯科検診では、歯科医師や歯科衛生士がご自身の口腔内の状態をチェックし、歯周病の早期発見に繋げます。また、専用の器具を使った専門的なクリーニングにより、ご自身では除去できない歯石や頑固な歯垢を取り除き、歯周病の進行を効果的に防ぐことができます。定期検診は、健康な口内環境を維持し、ひいては全身の健康を守るための重要な習慣となるでしょう。
歯科医院で行う専門的なクリーニング
歯科医院で行われる専門的なクリーニングの代表的な処置が「スケーリング」です。これは、歯周病の原因となる歯石を除去する処置を指します。歯石は、歯垢が唾液中のミネラルと結合して硬くなったもので、表面がザラザラしているため、さらに歯垢が付着しやすくなる悪循環を生み出します。
歯科衛生士は、スケーラーと呼ばれる専用の器具を用いて、歯の表面だけでなく、歯周ポケットの奥深くに隠れた歯石まで丁寧に徹底的に除去します。この処置によって、歯周病菌の温床となる歯石を取り除き、プラークが再付着しにくい滑らかな歯面を取り戻すことができます。また、クリーニング後は歯面の研磨も行い、さらにプラークが付きにくい状態に整えます。
歯周ポケットの検査
歯科検診で行われる「歯周ポケットの検査」は、「プロービング」とも呼ばれ、歯周病の進行度合いを正確に把握するために不可欠な検査です。この検査では、目盛りのついた細い器具であるプローブを歯と歯ぐきの間に優しく挿入し、その深さをミリ単位で測定します。
健康な歯ぐきの場合、歯周ポケットの深さは通常1〜3mm程度です。しかし、歯周病が進行すると歯ぐきが炎症を起こし、歯と歯ぐきの付着が破壊されて歯周ポケットが深くなり、4mm以上になることがあります。この検査によって、歯周病がどの程度進行しているか、どの部位に問題があるかを特定し、適切な治療計画を立てることができます。痛みはほとんどなく、歯周病の早期発見・早期治療のために非常に重要な検査ですので、安心して受けてください。
生活習慣の改善でリスクを減らす
歯周病は、プラーク(歯垢)が直接的な原因ですが、それに加えて、様々な生活習慣が歯周病の発症や進行に深く関わっています。日々の生活習慣を見直し、改善することで、歯周病のリスクを大幅に減らすことが可能です。口腔ケアだけでなく、体全体の健康を向上させる視点を持つことが、歯周病予防には欠かせません。
具体的なアクションプランとしては、まず「禁煙」が挙げられます。喫煙は歯肉の血流を悪化させ、免疫力を低下させるため、歯周病を進行させる最大の要因の一つです。次に、「バランスの取れた食事」を心がけましょう。栄養バランスの偏りは全身の抵抗力を弱め、歯肉の健康にも影響を与えます。また、「ストレス管理」や「十分な睡眠」も重要です。ストレスは免疫機能を低下させ、歯周病菌に対する抵抗力を弱めます。適度な運動を取り入れ、心身のリラックスを図ることも効果的です。これらの生活習慣の改善は、歯周病だけでなく、全身の健康維持にも繋がる大切な取り組みと言えるでしょう。
歯周病が疑われる場合は早めに歯科医院へ
ここまでお話ししてきたセルフチェックで、もし歯周病のサインに心当たりがあるようでしたら、放置することは大変危険です。歯周病は、一度発症すると自然に治癒することはありません。むしろ、徐々に進行して悪化の一途をたどる病気です。症状が軽い段階であれば、治療にかかる時間や費用、そして体への負担も少なく済むことがほとんどです。
「少し気になるけれど、まだ大丈夫だろう」と自己判断せずに、まずは専門家である歯科医師に相談することが非常に重要です。早期に適切な治療を開始することで、歯周病の進行を食い止め、大切な歯を守り、さらには全身の健康への悪影響を防ぐことができます。
歯科医院で行われる歯周病治療の流れ
歯周病の治療と聞くと、どのようなことをするのか不安に感じる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、多くの場合は段階を踏んで慎重に進められますのでご安心ください。一般的な歯周病治療は、主に以下のステップで進行します。
まず、「①検査・診断」として、レントゲン撮影や歯周ポケットの深さの測定などを行い、歯周病の進行度や原因を詳しく調べます。次に、「②歯周基本治療」へと移ります。ここでは、歯垢(プラーク)や歯石の徹底的な除去(スケーリング)と、ご自身で行う歯磨きの方法(ブラッシング指導)が行われます。これは治療の土台となる非常に大切なステップです。この基本治療後に「③再評価」を行い、歯周病の状態が改善されているかを確認します。
もし基本治療だけでは改善が見られない場合は、「④(必要に応じて)歯周外科治療」を行うこともあります。しかし、いきなり外科的な処置になるわけではなく、まずは丁寧な清掃とセルフケアの改善から始めるのが一般的です。治療が完了した後は、「⑤メンテナンス(定期検診)」として、再発防止のために定期的に歯科医院でチェックとクリーニングを続けることが推奨されます。
まとめ:口臭対策は歯周病ケアから始めよう
この記事では、多くの方が抱える口臭の悩みが、実は歯周病と深く関連している可能性について詳しく解説してきました。歯周病が歯ぐきや歯を支える骨を破壊していく病気であること、そして歯周病菌が口臭の主要な原因となるメカニズムについてご理解いただけたのではないでしょうか。また、ご自身でできるセルフチェックの方法や、歯周病を悪化させる様々なリスク要因、さらには放置することによる口臭以外の深刻なリスクについても触れてきました。
口臭対策の第一歩は、歯周病の予防と適切な管理から始まります。日々の丁寧なセルフケア(正しい歯磨き、歯間ブラシやデンタルフロスの活用)と、歯科医院での定期的なプロフェッショナルケア(専門的なクリーニングや歯周ポケット検査)を両立させることが、健康な口腔環境を維持し、全身の健康を守る上で非常に重要です。この情報が、皆さんが自信を持って笑顔で毎日を過ごすための一助となれば幸いです。
少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
近藤 光 | Kondo Hikaru東京歯科大学卒業後、医療法人社団歯友会赤羽歯科に勤務し、その後、池袋診療所をはじめとする複数の歯科医院で経験を積み、フリーランス矯正歯科医として活動を開始。
その後、カメアリデンタル、デンタルクリニックピュア恵比寿、茅ヶ崎アルカディア歯科・矯正歯科、フォルテはにゅうモール歯科、舞浜マーメイド歯科など、多くの歯科医院で勤務を重ね、2023年12月赤坂B&S歯科・矯正歯科 開院。
【所属】
- 日本顎咬合学会
- 日本審美歯科学会
- 日本成人矯正歯科学会
- 日本舌側矯正歯科学会
- 日本メタルフリー学会
- 日本接着歯科学会
- 日本アライナー矯正研究会
- 日本顎顔面美容医療協会 認定医
- ICOI(国際口腔インプラント学会)
- 日本一般臨床矯正研究会
- OTEXE
- インディアナ大学歯学部矯正科認定医
【略歴】
- 東京歯科大学 卒業
- 医療法人社団歯友会赤羽歯科
- 同法人池袋診療所 入局
- 医療法人スマイルコンセプト
- 高田歯科インプラントセンター
- しんみ歯科
- 医療法人社団優綾会カメアリデンタル 矯正歯科担当医
- デンタルクリニックピュア恵比寿 矯正歯科担当医
- 医療法人社団角理会 茅ヶ崎アルカディア歯科・矯正歯科 矯正歯科担当医
- 医療法人恵優会フォルテはにゅうモール歯科 矯正歯科担当医
- 舞浜マーメイド歯科 矯正歯科担当医
- 医療法人恵優会かすかべモール歯科 矯正歯科担当医
- レフィーノデンタルクリニック 矯正歯科担当医
- 医療法人社団カムイ会柏なかよし矯正歯科・小児歯科 矯正歯科担当医
港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科
『赤坂B&S歯科・矯正歯科』
住所:東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル1・2F
TEL:03-5544-9426

