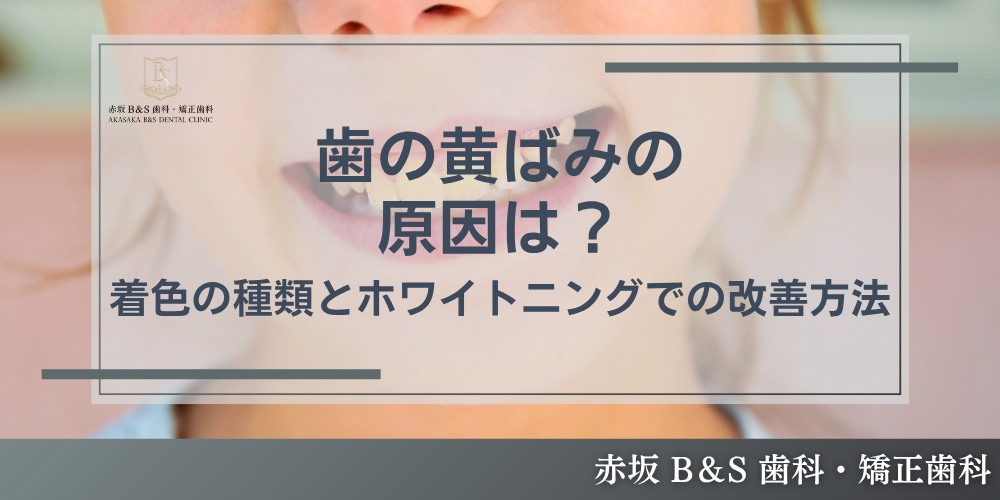
港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科「赤坂B&S歯科・矯正歯科」です。
歯の黄ばみは、見た目の印象に大きく影響を与える要因の一つです。
歯の色が気になるという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、歯の黄ばみの原因や着色の種類、そして歯の黄ばみを改善するための具体的な方法について詳しく解説します。
歯の色に関する悩みをお持ちの方や、歯の黄ばみ改善、予防に関心がある方は、ぜひ参考にしてください。
歯が黄ばむ主な要因
歯が黄ばむ原因はさまざまですが、大きく分けると歯の内部に原因がある「内因性」と、歯の外部からの影響による「外因性」、そして日々のケアに関連する要因に分類されます。
これらの歯の着色の理由を知ることで、適切な対策を講じ、歯の黄ばみの原因にアプローチすることが可能です。
ここでは、それぞれの要因について詳しく見ていきましょう。
歯の内部が影響する要因(内因性)
内因性とは、歯の内部構造や体質など、体の内側から影響を受ける歯の黄ばみの原因を指します。
これは、表面的な汚れとは異なり、歯そのものの色が変化している状態です。
内因性の黄ばみは、日頃の歯磨きだけでは改善が難しい場合が多いです。
生まれつきの歯の色や遺伝
歯の色は、もともと個人差が大きいものです。
これは主に歯の構造に関係しており、歯の表面を覆う半透明のエナメル質の内側にある象牙質の色が透けて見えるため、象牙質の色が濃い方は、生まれつき歯の色が黄色っぽく見えることがあります。
エナメル質の厚さにも個人差があり、エナメル質が薄い場合は、内側の象牙質の色がより透けて見えやすくなり、結果として内因性の歯の色が濃く見える傾向があります。
遺伝も歯の色に影響を与える要因の一つと考えられています。
年齢を重ねることによる変化
歯の色は、年齢を重ねることによっても変化します。
これは、加齢に伴い歯の表面のエナメル質が少しずつすり減り薄くなる一方で、内側の象牙質の色が濃くなっていくためです。
エナメル質が薄くなると、より一層象牙質の色が透けて見えるようになり、歯全体が黄色っぽく見えやすくなります。
このような老化による歯の黄ばみも内因性の一つと言えます。
歯の神経の状態
歯の神経(歯髄)の状態も、歯の変色に影響を与えることがあります。
例えば、虫歯が進行して歯の神経が死んでしまったり、過去の歯科治療によって神経を抜いたりした場合、歯の内部の色が変化して暗く見えることがあります。
また、外傷によって歯の神経がダメージを受けた場合も、内出血などにより歯が変色する可能性があります。
これらの変化も、内因性の歯の黄ばみの原因となり得ます。
歯の外部からの影響(外因性)
外因性とは、飲食物やタバコなど、歯の外部から付着する色素による歯の着色汚れを指します。
これは一般的に「ステイン」と呼ばれており、歯の表面に色素が沈着することで歯が黄ばんで見えます。
毎日の飲食や生活習慣が大きく影響するため、日頃のケアや食生活の見直しによってある程度の予防や改善が期待できます。
歯の黄ばみの原因の中でも比較的対処しやすい種類と言えるでしょう。
飲食物による色素の沈着
日常的に摂取する飲食物の中には、歯にステインとして着色しやすいものが数多くあります。
特に色の濃い飲み物や食べ物は注意が必要です。
例えば、コーヒーや紅茶、緑茶に含まれるタンニンやカテキン、赤ワインに含まれるポリフェノール、カレーやケチャップなどに含まれる色素は、歯の表面にあるペリクルという薄い膜と結合しやすい性質を持っています。
これらの飲食物を頻繁に摂取することで、ステインが歯に付着し、茶渋のように歯の着色汚れとして蓄積されていくのです。
飲食後すぐに口をゆすぐなど、意識的なケアが歯の着色を防ぐ上で重要となります。
これは外因性による黄ばみの代表的な原因の一つです。
喫煙による影響
喫煙も歯の黄ばみの大きな原因となります。
タバコに含まれるヤニ(タール)は非常に粘着性が高く、一度歯に付着すると落ちにくい性質があります。
ヤニは歯の表面にこびりつき、頑固なステインとなって歯を茶色く変色させます。
喫煙習慣がある場合、ヤニによる外因性の着色が進行しやすく、日頃の歯磨きだけでは除去が難しくなることが多いです。
禁煙は、歯の黄ばみを改善・予防する上で非常に効果的な方法と言えます。
日々のケアと関連する要因
日々の歯磨きや口腔ケアの状態も、歯の黄ばみの原因や歯の着色汚れの蓄積に大きく関わってきます。
適切なケアが行われていない場合、汚れが蓄積しやすく、結果として歯が黄ばんで見えることがあります。
日々の習慣を見直すことで、歯の黄ばみを予防し、改善につなげることが可能です。
歯磨きの精度
毎日の歯磨きは、歯の表面に付着した飲食物の色素やプラーク(歯垢)を除去し、歯の着色汚れを防ぐために非常に重要です。
しかし、歯磨きの方法が不適切だったり、磨き残しがあったりすると、汚れが歯の表面に残り、徐々に蓄積して黄ばみの原因となります。
特に歯と歯の間や歯と歯茎の境目などは磨き残しやすいため、デンタルフロスや歯間ブラシなどを併用して、歯のすみずみまで丁寧に磨くことが大切です。
適切な歯磨きを行うことで、外因性の歯の着色汚れを効果的に除去し、歯の黄ばみを予防できます。
虫歯の進行
虫歯も歯の黄ばみの原因となることがあります。
虫歯が進行すると、歯の質が変化し、黄ばんだり黒ずんだりすることがあります。
また、治療済みの歯に詰め物やかぶせ物をしている場合、その周りから再び虫歯が進行すると、詰め物やかぶせ物の変色や、歯自体の色の変化を引き起こすことがあります。
さらに、古い詰め物やかぶせ物自体が劣化して変色し、歯が黄ばんで見えることもあります。
虫歯の早期発見と適切な治療は、歯の健康を保つだけでなく、歯の変色を防ぐためにも重要です。
歯の黄ばみが与える印象
歯の色は、人の第一印象に大きな影響を与えます。
歯の黄ばみがあると、清潔感や健康的な印象が損なわれてしまうことがあります。
一方で、白く輝く歯は、明るく清潔な印象を与え、自信につながることも少なくありません。
このように、歯の色は見た目の美しさだけでなく、その人が周囲に与える印象にも深く関わっています。
歯の色が与える印象
歯の色は、相手に与える印象を大きく左右します。
例えば、歯が黄ばんでいると、不潔に見えたり、実年齢よりも老けて見られたりすることがあります。
これは、歯の黄ばみが喫煙や加齢と関連付けられることが多いためです。
逆に、白くきれいな歯は、清潔感があり、若々しく健康的な印象を与えます。
また、自信を持って笑顔を見せられるようになるため、コミュニケーションにおいてもポジティブな影響を与える可能性があります。
歯の色が与える印象は、単なる見た目の問題にとどまらず、その人の魅力や人間関係にも影響を及ぼす重要な要素と言えるでしょう。
歯の黄ばみを改善する方法
歯の黄ばみを改善し、歯を白くする方法には、ご自身で行えるセルフケアから、歯科医による専門的な処置まで様々な選択肢があります。
黄ばみの原因や程度、希望する白さのレベルによって、最適な方法は異なります。
ここでは、それぞれの歯の黄ばみ改善方法について詳しくご紹介します。
自宅で行えるケア
自宅で行えるセルフケアは、比較的気軽に始められる歯の黄ばみ改善方法です。
日々の歯磨きに取り入れたり、市販の製品を使用したりすることで、歯の表面の着色汚れにアプローチし、歯を白くする効果が期待できます。
ただし、セルフケアで改善できるのは主に外因性の着色汚れであり、内因性の黄ばみには効果が限定的な場合があります。
着色汚れに対応した歯磨き粉
市販されている歯磨き粉の中には、着色汚れを落とすことに特化した成分を配合しているものがあります。
例えば、ポリリン酸ナトリウムやピロリン酸ナトリウムといった成分は、歯の表面に付着したステインを浮き上がらせたり、再び付着するのを防いだりする効果が期待できます。
また、研磨剤が配合されている歯磨き粉は、物理的に歯の表面の汚れを削り落とす働きがありますが、研磨力が強すぎると歯を傷つける可能性もあるため、使用する際は注意が必要です。
着色汚れに対応した歯磨き粉を日々の歯磨きに取り入れることは、手軽に歯の黄ばみ改善を目指せるセルフケアの一つです。
歯の表面に塗る製品
歯の表面に直接塗布することで、歯を白く見せるセルフケア製品もあります。
これは、歯のマニキュアやホワイトニングペンといったもので、歯の表面に白い薬剤を塗ることで一時的に歯の色を白く見せる効果があります。
ただし、これらの製品は歯そのものを漂白するわけではないため、効果は限定的であり、時間の経過とともに剥がれたり、色むらが生じたりすることがあります。
あくまで一時的な対処法として、特別な機会に使用するといった方法が考えられます。
セルフケアとして手軽に試せる反面、効果の持続性や自然な白さという点では限界があります。
歯の表面を磨くアイテム
歯の表面の着色汚れを物理的に除去するセルフケアアイテムとして、歯の消しゴムやシリコンカップ付きの電動歯ブラシなどがあります。
これらのアイテムは、歯の表面を磨くことでステインを取り除く効果が期待できます。
ただし、強い力で擦りすぎたり、頻繁に使用したりすると、歯の表面のエナメル質を傷つけてしまう可能性があるため、使用方法には十分注意が必要です。
歯の表面の細かな傷は、かえって汚れが付着しやすくなる原因となることもあります。
適切な使用方法を確認し、歯を傷つけないように優しく行うことが、効果的なセルフケアのために重要です。
自宅で行うホワイトニング
自宅で行うホームホワイトニングは、歯科医院で処方された薬剤とマウスピースを使用して、ご自身で歯を白くする方法です。
歯科医師の指導のもと、自宅で継続的に行うことで、歯の内部の色素にアプローチし、歯の黄ばみ改善や自然な歯を白くする効果が期待できます。
ホームホワイトニングに使用される薬剤の主成分は過酸化尿素で、これが分解される際に発生する成分が歯の着色物質を分解し、歯を白くします。
効果が現れるまでに時間がかかりますが、ご自身のペースでできること、オフィスホワイトニングに比べて効果が持続しやすいというメリットがあります。
歯科医師の診断を受け、適切な薬剤の使用方法を確認した上で行うことが重要です。
セルフケアの中でも、歯の黄ばみ改善に比較的高い効果が期待できる方法の一つです。
歯科医院での専門的な処置
歯科医院で行う専門的な処置は、セルフケアでは難しい歯の黄ばみ改善や、より即効性のある歯を白くする方法として有効です。
歯科医による診断のもと、原因や歯の状態に合わせた適切な処置を受けることで、高い効果が期待できます。
様々な方法があるため、歯科医師と相談し、ご自身の希望に合った方法を選択することが重要です。
歯のクリーニング
歯科医院で行う歯のクリーニング(PMTC:ProfessionalMechanicalToothCleaning)は、専用の器具を使用して、歯の表面に付着したプラーク(歯垢)や歯石、そして飲食物による歯の着色汚れを徹底的に除去する処置です。
日常の歯磨きでは落としきれない汚れを専門的に除去することで、歯本来の色を取り戻し、歯の黄ばみを目立たなくする効果があります。
歯のクリーニングは、歯の表面の汚れを除去することが目的であり、歯の色自体を白く漂白する効果はありませんが、外因性の黄ばみに対しては高い効果が期待できます。
定期的に歯科医によるクリーニングを受けることは、歯の黄ばみ改善だけでなく、虫歯や歯周病の予防にもつながります。
歯科医院で行うホワイトニング
歯科医院で行うオフィスホワイトニングは、高濃度の過酸化水素を含む薬剤を使用し、特殊な光を当てることで歯を短時間で白くする方法です。
歯科医の管理のもとで行われるため、安全性が高く、即効性があるのが特徴です。
一度の施術でもある程度の歯を白くする効果が期待できますが、効果の持続期間はホームホワイトニングに比べて短い傾向があります。
短期間で歯の黄ばみ改善を実感したい場合や、結婚式などのイベントを控えている場合などに適しています。
歯科医による診断を受け、歯の状態や希望する白さに合わせて適切な濃度の薬剤を使用することが重要です。
両方を組み合わせた方法
オフィスホワイトニングとホームホワイトニングを組み合わせた「デュアルホワイトニング」という方法もあります。
まず歯科医院でオフィスホワイトニングを行い、ある程度の歯の黄ばみ改善効果を得た後、自宅でホームホワイトニングを継続することで、より高い歯を白くする効果と効果の持続を目指します。
即効性と持続性の両方を求める場合に有効な方法です。
歯科医と相談し、ご自身のライフスタイルや希望する白さのレベルに合わせて、デュアルホワイトニングを選択することも可能です。
その他の治療法
ホワイトニングで効果が得られない場合や、歯の形や位置も同時に改善したい場合には、その他の治療法が選択されることもあります。
例えば、セラミック製の薄い板を歯の表面に貼り付けるラミネートベニアや、歯全体をセラミック製の冠で覆うセラミッククラウンなどの方法があります。
これらの治療法は、歯の色だけでなく、歯の形や隙間なども同時に改善できるため、より審美性の高い歯を目指すことができます。
ただし、歯を削る必要がある場合もあるため、歯科医と十分に相談し、メリット・デメリットを理解した上で選択することが重要です。
これらの治療法も、歯の黄ばみ改善の一つの選択肢となります。
黄ばみを防ぐための対策
歯の黄ばみを改善することも大切ですが、そもそも歯の着色を防ぐことも非常に重要です。
日頃から意識して対策を行うことで、歯の黄ばみを予防し、白い歯を維持することができます。
ここでは、歯の黄ばみ対策として効果的な方法をご紹介します。
毎日の歯磨きの工夫
毎日の歯磨きは、歯の着色を防ぐための基本です。
ただ磨くだけでなく、いくつかの工夫をすることで、より効果的に歯の着色を防ぐことができます。
例えば、色素が沈着しやすい歯と歯の間や歯と歯茎の境目を意識して丁寧に磨くことが重要です。
歯ブラシだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシなども活用して、歯のすみずみまで汚れを除去しましょう。
また、着色予防効果のある歯磨き粉を使用するのも一つの方法です。
ただし、研磨剤の含有量が多い歯磨き粉は歯を傷つける可能性があるため、研磨剤の少ないものや、着色汚れを浮かせて落とす成分が配合された歯磨き粉を選ぶと良いでしょう。
正しい歯磨き習慣を身につけることが、歯の着色を防ぐ上で非常に効果的です。
着色しやすいものの摂取とケア
コーヒーや紅茶、緑茶、赤ワインなど、歯に茶渋のように着色しやすい飲み物や、カレーやケチャップなど色の濃い食べ物を摂取する際は、いくつか注意することで歯の着色を防ぐことができます。
例えば、これらの飲食物を摂取した後、できるだけ早く口を水でゆすいだり、歯磨きをしたりすることが効果的です。
すぐに歯磨きが難しい場合は、水を飲むだけでも、色素が歯に定着するのをある程度防ぐことができます。
また、ストローを使って飲み物を飲むことで、飲み物が歯に触れる機会を減らすことも有効な歯の着色を防ぐ方法です。
これらの工夫を日常生活に取り入れることで、歯の黄ばみ対策につながります。
唾液の働きを促す
唾液には、口の中の汚れを洗い流したり、歯の再石灰化を助けたりする自浄作用があります。
唾液の分泌量が少ないと、口の中が乾燥しやすくなり、汚れや色素が付着しやすくなります。
そのため、唾液の働きを促すことは、歯の着色を防ぐ上で重要です。
よく噛んで食事をしたり、シュガーレスガムを噛んだりすることで、唾液の分泌を促進することができます。
また、こまめに水分を摂ることも、口の中の乾燥を防ぎ、唾液の働きを助けることにつながります。
唾液の分泌を意識することは、歯の健康を保ち、歯の着色を防ぐためにも役立ちます。
定期的な歯科検診
定期的に歯科医院で検診を受けることも、歯の着色を防ぐために重要です。
歯科医師や歯科衛生士によるプロフェッショナルクリーニングを受けることで、日頃の歯磨きでは落としきれない歯石や歯の着色汚れを除去してもらうことができます。
また、定期検診では虫歯や歯周病のチェックも行われるため、歯の健康状態を維持するためにも重要です。
歯科医から適切な歯磨き指導を受けることもできるため、ご自身の歯磨きの癖や磨き残しやすい部分を知り、日々のケアに活かすことができます。
定期的な歯科医への受診は、歯の着色を防ぐだけでなく、お口全体の健康維持につながります。
避けるべき黄ばみケア
歯の黄ばみを改善したいという一心で、誤った方法を試してしまうと、かえって歯を傷つけたり、黄ばみを悪化させたりする可能性があります。
効果がないだけでなく、歯の健康を損なうリスクもあるため、避けるべき黄ばみケアについて知っておくことが重要です。
正しい知識を持ち、安全な方法でケアを行いましょう。
重曹や塩での歯磨き
インターネットなどで、重曹や塩を使った歯磨きが歯の黄ばみ対策に効果があるといった情報を見かけることがありますが、これは避けるべき方法です。
重曹や塩は研磨作用がありますが、粒子が粗いため、歯の表面のエナメル質を傷つけてしまう可能性があります。
エナメル質に傷がつくと、かえって汚れや色素が付着しやすくなり、歯の黄ばみを悪化させる原因となることがあります。
また、知覚過敏を引き起こす可能性もあります。
歯の表面を傷つけずに汚れを除去するためには、歯磨き粉を使用する場合も研磨剤の量や種類に注意が必要です。
安全で効果的な歯の黄ばみケアのためには、これらの方法を避けるようにしましょう。
酸性の物質の使用
酢やクエン酸など、酸性の強い物質を歯の黄ばみ対策に使用することも危険です。
酸性の物質は歯の表面のエナメル質を溶かしてしまう性質(脱灰)があります。
エナメル質が溶けると、歯の表面がroughになり、色素が付着しやすくなるだけでなく、歯が弱くなり虫歯のリスクも高まります。
レモン汁で歯を磨くといった方法も同様に危険ですので、絶対に避けるべきです。
歯のエナメル質は一度溶けてしまうと元には戻らないため、酸性の物質を歯に直接塗布したり、これらを使った歯磨きをしたりすることは絶対にやめましょう。
研磨剤の使用
歯磨き粉には研磨剤が含まれているものが多いですが、過度な研磨剤の使用は避けるべきです。
研磨剤は歯の表面の汚れを落とす効果がありますが、その程度が強すぎると、歯の表面のエナメル質を削りすぎてしまう可能性があります。
エナメル質が薄くなると、内側の黄色い象牙質が透けて見えやすくなり、結果として歯の黄ばみが目立つことがあります。
また、歯の表面に細かい傷がつき、かえって汚れが付着しやすくなる悪循環に陥ることもあります。
特に、タバコのヤニ取りを謳っている強力な研磨剤入りの歯磨き粉などは、歯を傷つけるリスクが高いため注意が必要です。
歯磨き粉を選ぶ際は、研磨剤の種類や量を確認し、歯に優しいものを選ぶようにしましょう。
少しでも参考になれば幸いです。
本日も最後までお読みいただきありがとうございます。
監修者
近藤 光 | Kondo Hikaru 東京歯科大学卒業後、医療法人社団歯友会赤羽歯科に勤務し、その後、池袋診療所をはじめとする複数の歯科医院で経験を積み、フリーランス矯正歯科医として活動を開始。その後、カメアリデンタル、デンタルクリニックピュア恵比寿、茅ヶ崎アルカディア歯科・矯正歯科、フォルテはにゅうモール歯科、舞浜マーメイド歯科など、多くの歯科医院で勤務を重ね、2023年12月赤坂B&S歯科・矯正歯科 開院。【所属】
- 日本顎咬合学会
- 日本審美歯科学会
- 日本成人矯正歯科学会
- 日本舌側矯正歯科学会
- 日本メタルフリー学会
- 日本接着歯科学会
- 日本アライナー矯正研究会
- 日本顎顔面美容医療協会 認定医
- ICOI(国際口腔インプラント学会)
- 日本一般臨床矯正研究会
- OTEXE
- インディアナ大学歯学部矯正科認定医
【略歴】
- 東京歯科大学 卒業
- 医療法人社団歯友会赤羽歯科
- 同法人池袋診療所 入局
- 医療法人スマイルコンセプト
- 高田歯科インプラントセンター
- しんみ歯科
- 医療法人社団優綾会カメアリデンタル 矯正歯科担当医
- デンタルクリニックピュア恵比寿 矯正歯科担当医
- 医療法人社団角理会 茅ヶ崎アルカディア歯科・矯正歯科 矯正歯科担当医
- 医療法人恵優会フォルテはにゅうモール歯科 矯正歯科担当医
- 舞浜マーメイド歯科 矯正歯科担当医
- 医療法人恵優会かすかべモール歯科 矯正歯科担当医
- レフィーノデンタルクリニック 矯正歯科担当医
- 医療法人社団カムイ会柏なかよし矯正歯科・小児歯科 矯正歯科担当医
港区赤坂・赤坂見附の歯医者・矯正歯科
『赤坂B&S歯科・矯正歯科』
住所:東京都港区赤坂3-2-2 日総第24ビル1・2F
TEL:03-5544-9426

